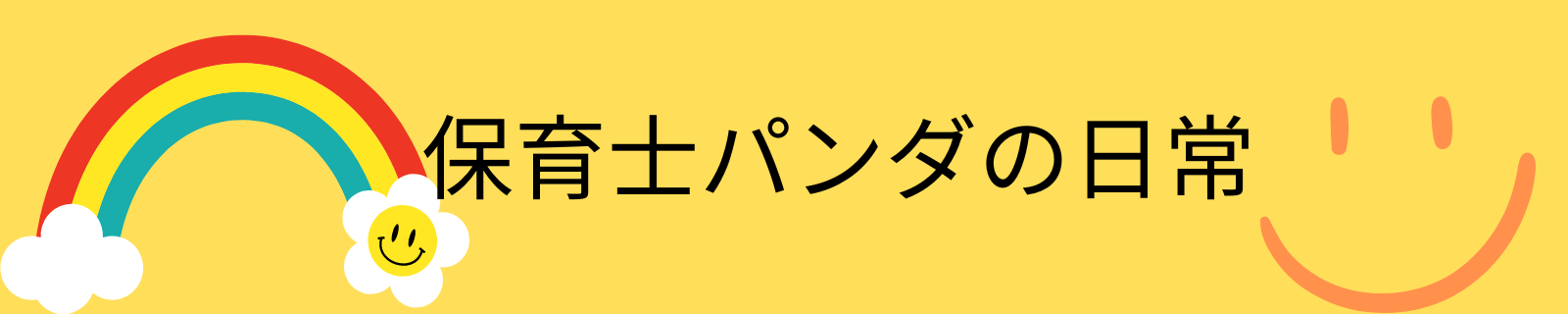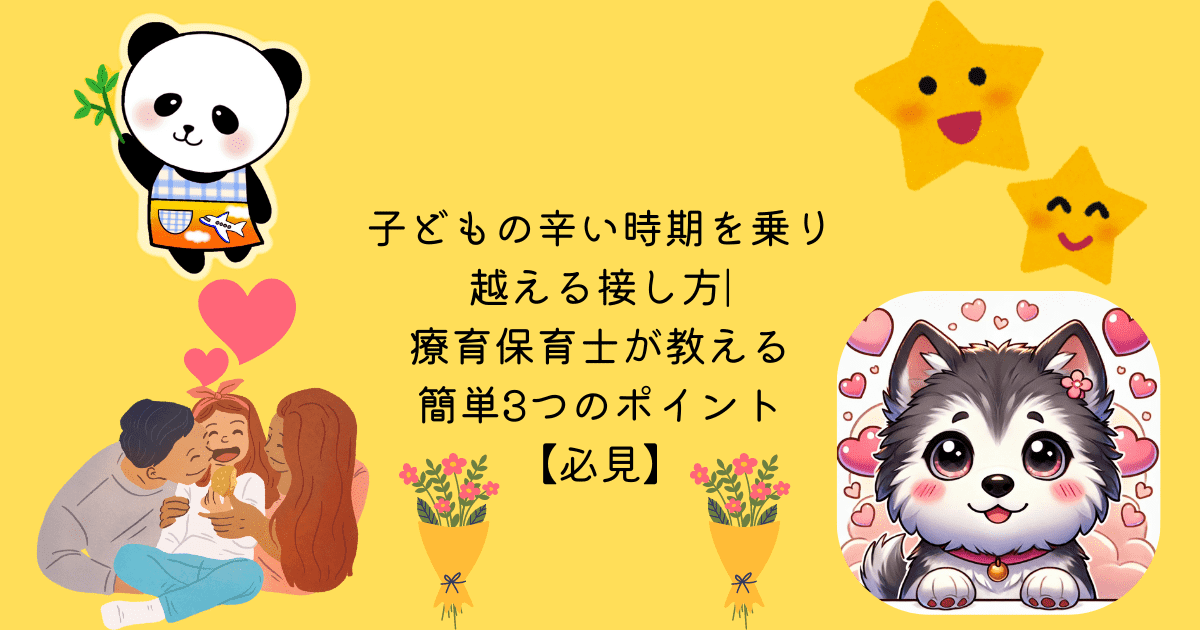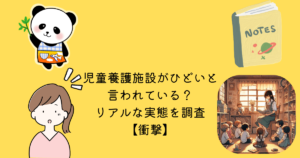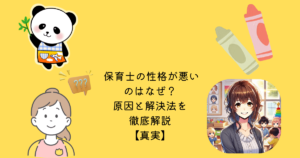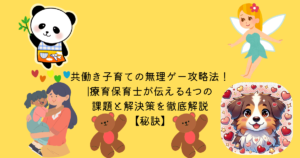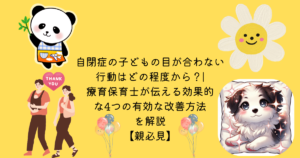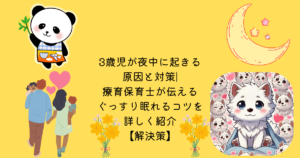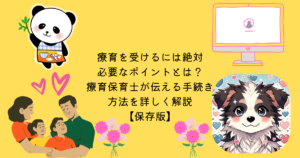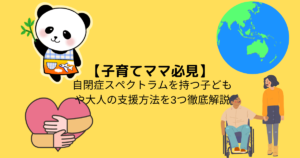悩むペンさん
悩むペンさん子どもが辛い時に親はどうすれば
良いの?



保育士パンダ(@pannda_blog21)です。
そのお悩みを解決していくね!
- 療育保育士が伝える|子どもが辛そうなときの5つの接し方
- 療育保育士が伝える|子どもの辛い気持ちを和らげる7つの接し方テクニック
- 療育保育士が伝える|子どもが辛いときに親が気をつけるべき3つのポイント
「子どもが辛そう…でも、どう接したらいいの?」
そんな悩みを抱えているあなた。
子育ては楽しいことばかりではありませんよね。
子どもの気持ちが理解できず、適切な接し方がわからないことも
多いのではないでしょうか。
でも、大丈夫です。
子どもが辛いときの接し方には、実は効果的なテクニックがあるんです。
この記事では、子どもの心に寄り添い、辛い気持ちを和らげる方法を詳しく紹介します。
これを読めば、あなたも子どもとの絆を深め、より良い親子関係を築けるようになりますよ。
子どもの笑顔を取り戻すための秘訣、今すぐ見てみませんか?
保育士資格を取得した内容については、下記の記事が参考になります。
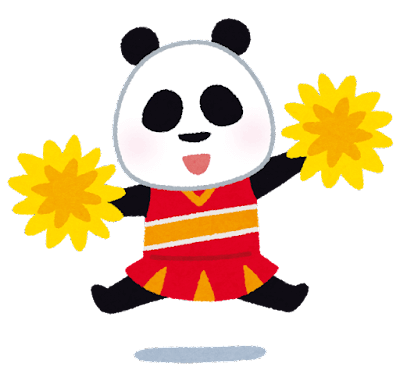
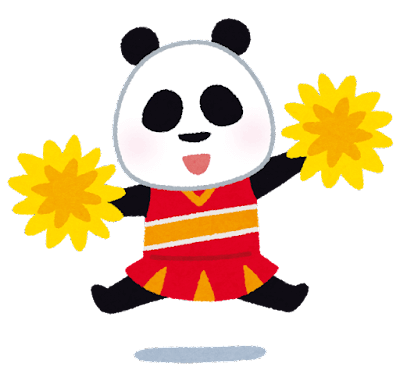
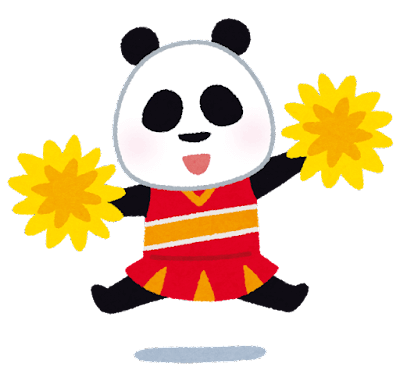
よかったら覗いてみてね!
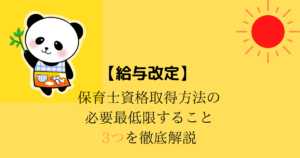
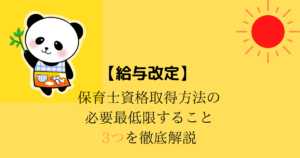
1.療育保育士が伝える|子どもが辛そうなときの5つの接し方


子どもが辛そうなときの5つの接し方について説明します。
- 辛さに気づくサイン
- 気持ちを受け止める方法
- 信頼関係を築く
- 年齢別サポート方法
- 療育保育士への相談
保育士給与の現状と課題については、下記の記事が参考になります。



よかったら覗いてみてね!
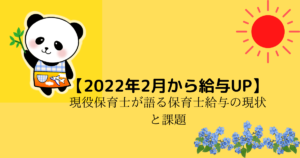
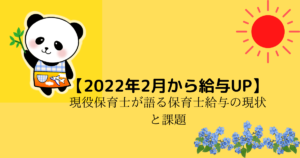
① 辛さに気づくサイン
子どもの辛さに気づくことは、とても大切です。
子どもが辛いときには、普段と違う様子が見られることがあります。
例えば、いつもより元気がない、食欲がない、よく泣く、イライラしている
などのサインがあります。
- 感情によるサインを見逃さない(年齢によって異なるため)
- 幼い子どもは体調の変化や行動の変化に注目
- 小学生くらいになると、友達関係の悩みや学校での出来事が原因で辛い思いをする
- 日頃から子どもの様子をよく観察し、変化に気づく努力が大切
子どもの辛さに早く気づくことで、適切なサポートを提供できるようになります。
② 気持ちを受け止める方法
子どもの辛い気持ちを受け止めるのは、親の大切な役割です。
子どもの気持ちを受け止めるには、まず、子どもの話をじっくり聞くことが大切です。
- 子どもが話し始めたら、途中で口をはさまずに最後まで聞く
- 子どもの気持ちを否定したり、軽く考えたりせずに、真剣に受け止めることが重要
- 「そう感じたんだね」「辛かったんだね」といった共感の言葉をかけてあげる
- 子どもの気持ちを言葉で表現してあげることも効果的
- 「友達に無視されて悲しかったんだね」といった具合に、子どもの気持ちを代弁してあげる
- 子どもは自分の気持ちを理解してもらえたと感じ、安心することができる
また、子どもの気持ちを受け止める際は、身体の姿勢も大切です。
子どもの目線の高さまで体を低くして、優しい表情で接することで、子どもは安心して
気持ちを話せるようになります。



子どもに根気強く寄り添い続ける
ことが大切なんだね!
③ 信頼関係を築く
子どもとの信頼関係を築くことは、子どもの辛い気持ちに寄り添う上で非常に重要です。
信頼関係を築くには、日頃からコミュニケーションを大切にし、子どもの気持ちを
尊重することが欠かせません。
- 子どもと一緒に過ごす時間を意識的に作る
- 食事の時間や寝る前のひとときなど、子どもと向き合う時間を確保することが大切
- 子どもの話をじっくり聞いたり、一緒に遊んだりすることで、絆を深める
- 子どもの言動を否定せずに、まずは受け入れる姿勢を持つことも重要
- 子どもの気持ちを尊重し、選択肢を与えることも効果的
- 「公園に行く?それとも図書館に行く?」と子どもに選択肢を与えたりすること
子どもの言動を否定せずに、まずは受け入れる姿勢を持つことも重要です。
子どもが間違ったことをしても、すぐに叱るのではなく、なぜそうしたのかを聞いてみましょう。
否定することは大人がやりがちなことなので、子どもとまず向き合うことが大事だと
療育保育士の私は強く思います。
このような小さな積み重ねが、長期的な信頼関係につながっていきます。
④ 年齢別サポート方法
子どもの年齢によって、辛いときのサポート方法は異なります。
年齢に応じた適切なサポートを行うことで、子どもの辛い気持ちを効果的に和らげることができます。
- 乳幼児期(0~5歳)の子どもの場合、言葉でのコミュニケーションが難しいため、スキンシップが重要
- 抱っこやおんぶ、優しい声かけなどで、安心感を与える
- 絵本の読み聞かせなどを通じて、感情表現の方法を教えることも効果的
- 小学生(6~12歳)の子どもには、言葉でのコミュニケーションがより重要
- 子どもの話をしっかり聞き、共感的な態度で接することが大切
- 問題解決のスキルを教えることも有効
- 「どうしたらいいと思う?」と子どもに考えさせ、一緒に解決策を探ることで、自信をつけさせる
- 中高生(13~18歳)になると、友人関係や学業、将来の不安など、悩みが複雑化する
- 子どもの自立心を尊重しながら、適度な距離感を保つことが重要
子どもが相談してきたときは、じっくり聞き、アドバイスを求められたら適切な
アドバイスを提供しましょう。
また、専門家のカウンセリングを勧めることも検討してみてください。
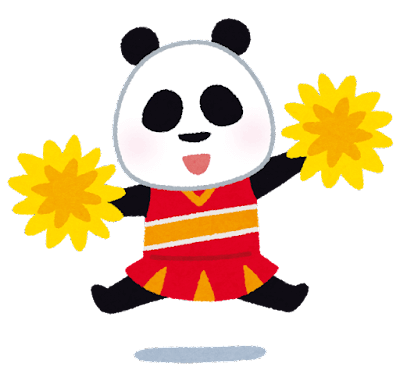
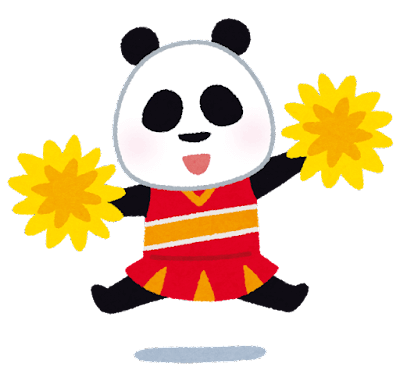
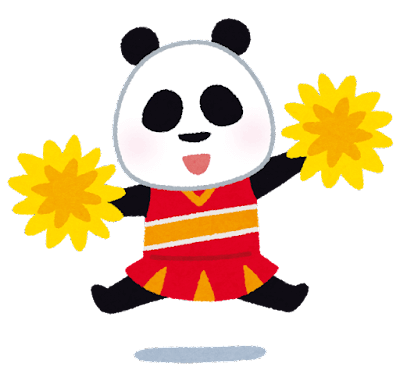
一人ひとりの子どもに合った
接し方を見つけていこうね!
⑤ 療育保育士への相談
子どもの辛さが長期化したり、対応に困ったりした場合は、専門家である
療育保育士に相談することをおすすめします。
療育保育士は、子どもの発達や行動に関する専門的な知識を持っており
適切なアドバイスを提供してくれます。
療育保育士への相談のタイミングとしては、以下のような場合が考えられます。
- 子どもの辛そうな様子が長期間(1ヶ月以上)続いている
- 子どもの行動や感情の変化が極端で、日常生活に支障をきたしている場合も相談の対象
- 具体的なエピソードを伝えることで、より適切なアドバイスを受けることができる
- 療育保育士との面談では、子どもの良いところも伝えることを忘れずにする
療育保育士との相談を通じて、子どもへの理解が深まり、より適切なサポート
ができるようになります。
専門家の助言を積極的に取り入れ、子どもの成長を支えていきましょう。
2.療育保育士が伝える|子どもの辛い気持ちを和らげる7つの接し方テクニック


子どもの辛い気持ちを和らげる7つの接し方テクニックについて説明します。
- 共感的な傾聴
- スキンシップの効果
- 長所を褒める
- 問題解決を一緒に考える
- リラックス環境の作り方
- 遊びでストレス発散
- 専門的アプローチ
保育所と事業所の違いについては、下記の記事が参考になります。



よかったら覗いてみてね!
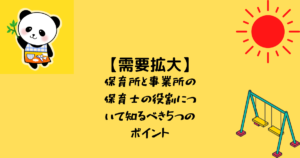
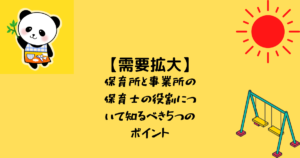
① 共感的な傾聴
共感的な傾聴は、子どもの辛い気持ちを和らげる上で非常に重要なテクニックです。
共感的な傾聴とは、子どもの話をただ聞くだけでなく、その気持ちに寄り添い
理解しようとする姿勢のことです。
- 子どもが話し始めたら、すべての作業を止めて、子どもに集中することが大切
- 子どもの目線の高さまで体を低くし、優しい表情で接することが重要
- 子どもの話を聞く際は、途中で口をはさまずに最後まで聞く
- 「そうだったんだね」「辛かったんだね」といった共感の言葉をかけてあげる
- 子どもの気持ちを言葉で表現してあげることも効果的
「友達に仲間はずれにされて寂しかったんだね」といった具合に
子どもの気持ちを代弁してあげましょう。
このような共感的な傾聴を通じて、子どもは自分の気持ちを理解してもらえたと感じ
心が軽くなります。
② スキンシップの効果
スキンシップは、子どもの辛い気持ちを和らげる上で非常に効果的なテクニックです。
優しく触れること、抱きしめることは、子どもに安心感を与え、ストレスを軽減する効果があります。
- スキンシップには、オキシトシンというホルモンの分泌を促進する効果がある
- オキシトシンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、ストレスを軽減し、安心感を高める働きがある
- スキンシップは言葉では表現しきれない愛情を伝える手段としても重要
- 言葉よりも体の触れ合いを通じて、親の愛情をより直接的に感じ取ることができる
日常生活の中でスキンシップを取り入れる方法はたくさんあります。
例えば、子どもの肩や背中をさすったり、寝る前に抱きしめたり、一緒に手をつないで
散歩したりするのも良いでしょう。
子どもが嫌がるようであれば、無理強いせず、タイミングを見計らって行いましょう。



スキンシップは愛情表現の大切な方法の
一つになるね!
③ 長所を褒める
子どもの長所を褒めることは、辛い気持ちを和らげる効果的なテクニックの一つです。
適切な褒め方は、子どもの自尊心を高め、自信を持たせることができます。
- 具体的な行動や努力を褒めることが大切
- 「難しい問題を最後まで諦めずに解こうとしたね」といった具体的な褒め方の方が効果的
- 結果だけでなくプロセスを褒めることも重要
- 「毎日コツコツ勉強を続けたからこその結果だね」と努力のプロセスを褒めてあげる
- 子どもの性格や特徴を褒めることも効果がある
- 「優しい子だね」「思いやりがあるね」といった言葉は、子どもの自己肯定感を高める
過度な褒め言葉は、かえって子どもにプレッシャーを与えたり、褒められることへの依存を
生んだりする可能性があります。
適度に、そして心からの言葉で褒めることが大切です。
また、褒める際は、子どもの目を見て、笑顔で接することも忘れずに。
非言語コミュニケーションも、メッセージを効果的に伝える上で重要です。
子どもの長所を褒めることで、辛い気持ちを和らげるだけでなく
前向きな姿勢や自信を育むことができます。
④ 問題解決を一緒に考える
子どもが辛い状況に直面したとき、問題解決を一緒に考えることは非常に効果的なアプローチです。
子どもと一緒に問題解決を考えることで、子どもの思考力を育てると同時に、自信をつけさせることができます。
- 子どもが抱えている問題を明確にすること
- 「今、何が一番辛い?」「どんなことで困っているの?」といった質問を通じて、問題の本質を理解する
- 子どもに「どうしたらいいと思う?」と尋ね、自分で解決策を考えるよう促す
- 子どもの意見をしっかり聞き、否定せずに受け止めることが重要
- 子どもが解決策を思いつかない場合は、いくつかの選択肢を提示してあげる
- 「いつ」「どこで」「どのように」行動するかを、子どもと一緒に考える
- うまくいった点、難しかった点を一緒に振り返り、次につなげる学びを得ることが大切
そして、実行後には必ずフォローアップを行います。
この過程を通じて、子どもは問題解決のスキルを身につけ、自信を持つことができます。
また、親が寄り添ってくれているという安心感も得られます。
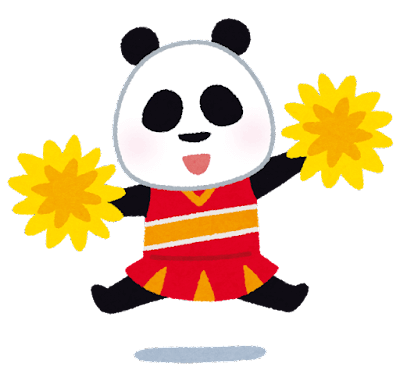
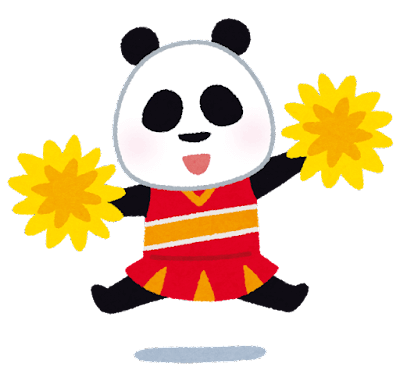
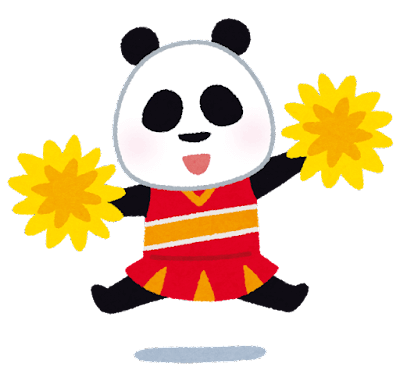
子どもの力を信じ、サポートする姿勢を
大切にしていかないとね!
⑤ リラックス環境の作り方
子どもが辛いときこそ、リラックスできる環境を整えることが重要です。
適切なリラックス環境は、子どものストレスを軽減し、心の安定をもたらします。
- 子どもの好きな場所や物を活用する
- 部屋の照明も重要
- 明るすぎず暗すぎない、柔らかな光の中で過ごすことで、子どもはリラックスしやすくなる
- ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のある香りを使用すると、子どもの心を落ち着かせる
- 適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠は、子どものストレス耐性を高める
- 就寝前のルーティンは重要
- 毎晩同じ流れを作ることで、子どもは安心して眠りにつく
さらに、家族で過ごす時間を大切にすることも、リラックス環境づくりの一環です。
テレビやスマートフォンを消して、家族で会話を楽しむ時間を作りましょう。
このような環境づくりを通じて、子どもは心身ともにリラックスし
辛い気持ちを和らげることができます。
⑥ 遊びでストレス発散
遊びは子どものストレス発散に非常に効果的です。
適切な遊びを通じて、子どもは楽しみながら自然とストレスを発散することができます。
- 身体を動かす遊びは大いに効果がある
- 運動することで脳内にエンドルフィンが分泌され、幸福感が高まる
- 創造的な遊びも有効
- 絵を描いたり、粘土で何かを作ったりする活動は、ストレス解消につながる
- ごっこ遊びも、子どもの心理的ストレスを和らげる効果がある
- 自然の中での遊びも推奨されている
- 森や海、川などで遊ぶことで、子どもはリフレッシュし、心を落ち着かせること
- 親子で一緒に遊ぶことも重要
ただし、遊びを強制するのは逆効果です。
子どもの気分や興味に合わせて、適切な遊びを選ぶことが大切です。
遊びを通じてストレスを発散することで、子どもは心身ともにリフレッシュし
辛い気持ちを和らげることができます。



楽しみながらストレス発散できる遊びを
子どもと一緒に見つけていきたいね!
⑦ 専門的アプローチ
子どもの辛い気持ちが長期化したり、深刻化したりした場合は、専門家のアプローチを検討することも重要です。
専門家は、子どもの心理や発達に関する深い知識を持ち、適切な支援方法を提案することができます。
- スクールカウンセラーへの相談
- 児童相談所も重要な相談先の一つ
- 心理療法士による遊戯療法も効果的な方法の一つ
- 遊戯療法では、子どもが遊びを通して自分の気持ちを表現し、心の問題を解決していく
- 発達障がいが疑われる場合は、小児科医や児童精神科医の診断を受けることも検討する必要がある
療育保育士にもいつでも相談して大丈夫です。
言葉の発達の遅れや子どもと目線が合わないなど、子ども自身も辛いことがありますが
親も辛い気持ちが必ずあります。
具体的なエピソードを伝えることで、より適切なアドバイスを受けることができます。
専門家の支援を受けることで、子どもの辛い気持ちを和らげるだけでなく
長期的な心の健康を支えることができます。
3.療育保育士が伝える|子どもが辛いときに親が気をつけるべき3つのポイント


子どもが辛いときに親が気をつけるべき3つのポイントについて説明します。
- 適度な距離感
- 一貫した態度の重要性
- 親のメンタルケア
児童発達支援と放課後等デイサービスについては
下記の記事が参考になります。



よかったら覗いてみてね!
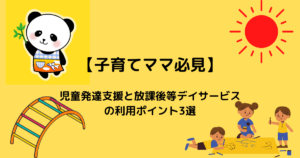
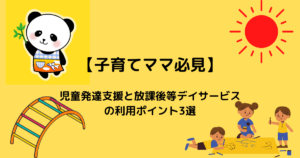
① 適度な距離感
子どもが辛いときに親が適度な距離感を保つことは、非常に重要です。
過保護になりすぎず、かといって放任しすぎず、子どもの自立心を育てながらサポートすることが大切です。
まず、子どもの年齢や性格に応じて、適切な距離感を見極める必要があります。
幼い子どもの場合は、より密接な関わりが必要かもしれません。
一方、思春期の子どもの場合は、ある程度の自由と責任を与えることが大切です。
子どもが自分で問題解決を試みる機会を与えることも重要です。
すぐに親が介入するのではなく、まずは子ども自身に考えさせ、行動させてみましょう。
「困ったときはいつでも相談していいよ」というメッセージを日頃から伝えておくことが大切です。
また、子どものプライバシーを尊重することも適度な距離感を保つ上で重要です。
特に思春期以降の子どもの場合、自分の部屋や持ち物に対するプライバシーを重視する傾向があります。
適度な距離感を保つことで、子どもは安心感と自立心のバランスを取ることができます。
② 一貫した態度の重要性
子どもが辛いときに親が一貫した態度を示すことは、非常に重要です。
一貫した態度は、子どもに安心感と信頼感を与え、心の安定につながります。
まず、家庭内のルールや約束事を明確にし、それを守り続けることが大切です。
例えば、就寝時間や勉強時間、スマートフォンの使用時間などのルールを決めたら、親自身もそれを尊重し、一貫して実行しましょう。
また、子どもの行動に対する評価や反応も一貫していることが重要です。
ある日は褒めて、別の日は同じ行動を叱るといった態度の変化は、子どもに混乱を与えます。
感情的になりすぎず、冷静に対応することを心がけましょう。
特に、子どもが辛い状況にあるときは、親の一貫した態度がより重要になります。
例えば、「大丈夫だよ」と言いながら、表情や態度が不安そうだと、子どもは親の言葉を信じられなくなります。
言葉と態度を一致させることが大切です。
また、両親間での態度の一貫性も重要です。
父親と母親で異なる対応をすると、子どもは混乱し、不安定になってしまいます。
両親で話し合い、子どもへの対応方針を統一することが大切です。
これにより、辛い状況を乗り越える力を育むことができるのです。
③ 親のメンタルケア
子どもが辛い状況にあるとき、親自身のメンタルケアも非常に重要です。
親が心身ともに健康であることが、子どもを適切にサポートする基盤となります。
まず、親自身のストレス管理が大切です。
子どもの問題に向き合う中で、親もストレスを感じることがあります。
そんなときは、深呼吸やストレッチ、軽い運動など、自分なりのリラックス方法を見つけましょう。
また、十分な睡眠と栄養バランスのとれた食事も、親のメンタルヘルスを保つ上で重要です。
親同士のコミュニケーションも大切です。
配偶者や他の家族メンバーと、子どもの状況や自分の気持ちについて話し合うことで、ストレスを軽減できます。
また、同じような経験をしている他の親との交流も有効です。
親の会や支援グループなどに参加することで、情報交換や心の支えを得ることができます。
必要に応じて、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
カウンセラーや心理療法士との面談は、親自身の心の整理や新たな視点の獲得に役立ちます。
自分を責めすぎないことも重要です。
完璧な親はいません。
自分のできる範囲で最善を尽くすことが大切です。
時には息抜きの時間を作り、自分の趣味や楽しみを持つことも
良好なメンタルヘルスを保つ上で効果的です。
親が心身ともに健康であることで、子どもに対してより適切なサポートを提供することができます。
まとめ|子どもが辛いときの適切な接し方
ここまでの内容をまとめると、以下のようになります。
| 接し方のポイント | 具体的な方法 |
|---|---|
| 気づきと傾聴 | 辛さのサインに注意、共感的な傾聴 |
| 気持ちの受け止め | 否定せず、共感の言葉をかける |
| 信頼関係の構築 | 日常的なコミュニケーション、子どもの意見尊重 |
| 年齢別サポート | 乳幼児期はスキンシップ、学童期は言葉でのコミュニケーション |
| リラックス環境 | 好きな場所や物の活用、規則正しい生活リズム |
| 遊びの活用 | 体を動かす遊び、創造的な遊び |
| 専門家の活用 | 必要に応じてカウンセラーや医師に相談 |
子育ての悩みは尽きませんが、一つずつ丁寧に向き合っていくことで
より良い親子関係を築いていくことができるでしょう。



分からないことがあれば
いつでも保育士パンダ(@pannda_blog21)
に聞いてね!
これからもよろしくね!
少しでもこの記事が誰かの役に立ったら嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。